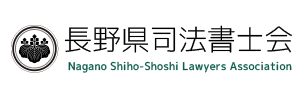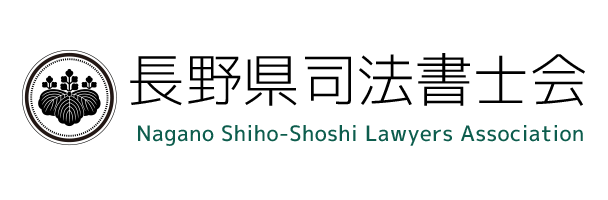少額トラブルについてよくあるご質問:
皆さんが、日々の生活の中で、計らずも何らかのトラブルに遭遇してしまった時に、私たち司法書士は、皆さんの相談を受け、問題解決に向けて、裁判所の扱う各種手続についてのアドバイスを提供することができます。 その際、皆さん自身が裁判手続をする場合、私たち司法書士は、裁判所への提出書類(訴状、その他各種申立書など)を作成したり、手続の流れなどのアドバイスを提供することで、皆さんをサポートすることができます。 (弁護士に依頼せず、あなた自身が訴訟を起こし、自分で裁判所に行って相手と争う裁判のことを、「本人訴訟」と言います。特に簡易裁判所で争われる裁判の約8割が、この本人訴訟です。) さらに、法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟、民事調停、仲裁事件、裁判外の和解などの代理人となって、皆さんに代わり、問題の解決に向けて裁判手続を進めることができます。
- 少額のトラブルの際に、裁判所で取り扱う手続には、どのようなものがありますか。
- 友人にお金を貸したけれど、そろそろ返して欲しい。どうしたらよいでしょうか。
- 家賃を滞納しているので、賃借人に出て行ってもらいたいのですが。
Q. 少額のトラブルの際に、裁判所で取り扱う手続には、どのようなものがありますか。
簡易裁判所で取り扱う民事手続は以下のとおりです。紛争の実体、あなたの意向、相手方との関係や状況など、いろいろな実情を踏まえて、どのような手続によることが問題の解決に最も良いかを判断して、選択することになります。
- 通常訴訟と少額訴訟
今までの訴訟手続きによると、解決までに何年もかかったり、訴訟によって求める額が少額の場合は、費用倒れになったりすることがありました。そこで、平成10年1月から「少額訴訟手続」制度が施行されました。これは、簡易裁判所において訴訟の目的の価格が60万円以下の金銭の支払いを請求するものであれば、今までの裁判手続きよりも簡便でスピーディーな紛争解決(原則として即日判決。)を選択することができる手続きです。
少額訴訟の判決後には、原則として控訴ができません。ただし、不服がある場合は同じ裁判所に異議の申立てができます。証拠は、その場で調べられるものに限ります。証人は、当日法廷に立てる人が原則です。申立ては同一の裁判所に一人、同一の年に10回までと限られています。
また、注意する点として、証拠や証人が揃っていて争点が少ないものであることが大切です。たとえば「クリーニングでシミがついた。」といった場合は、いつシミがついたのか証明しづらいので、少額訴訟には向いていません。
簡易裁判所は、請求認容の判決をする場合、被告の支払い能力等を考慮して、判決言い渡しの日から3年を超えない範囲内で、支払の猶予や分割払いの定めをすることができ、さらに訴え提起後の遅延損害金を免除することもできます。 - 支払督促
支払督促は、金銭等の支払請求について、簡易・迅速に、かつ、低廉な費用により、債権者に債務名義(強制執行ができる効力)を得させて、事件の処理をすることを目的とする手続です。
一般的には、金銭債権について、しかも請求自体には争いがない場合に利用されることが多いといえます。請求権自体に争いがある場合は、あまり効果がありません。お金を貸したのに期限が過ぎても返してくれない。しかし、訴えを提起していたのでは費用と時間がかかってしまう。そんな時に利用されます。
債権者からすれば、比較的簡単に手続きをすることができ、証拠等の提出も必要ないので、利用しやすい手続きの一つです。また、債務者にすれば裁判所から書類が送られてきますので、心理的圧迫を覚えます。その結果すぐにお金を返してくるケースもあります。
支払督促が到達して2週間を経過しますと強制執行される可能性がありますので、債務者の方は注意が必要です。 - 民事調停
調停とは、当事者と調停委員と呼ばれる人を交えた話し合いの場です(裁判官と当事者だけで行うこともできます)。双方に多少の譲歩する気持ちがある場合に効果的といえます。調停の注意点としては、自分の意思や請求をはっきり主張すること、調停で成立した内容について、自分の思いと違っていないか、しっかり確認することが大切です。調停で成立した合意内容を記載した調停調書は、判決と同じ効果があります。
Q. 友人にお金を貸したけれど、そろそろ返して欲しい。どうしたらよいでしょうか。
- 例えば、お金を貸す際、返済の時期を約束していない場合、まずは借主に対して、相当な期間を定めて、その期限までに返済するよう催告(請求)をします。
この催告は、後に裁判などで証拠資料となることを踏まえて、配達証明付の内容証明郵便でするのが良いでしょう。 - この時、注意すべきこととして「消滅時効」の問題があります。貸金債権は、民法上、権利を行使(返還請求)できる時から5年を経過すると、時効により消滅してしまいます。そのため、この消滅時効期間が経過する前に、催告しなければなりません。(注:民法改正により、2020年4月1日から貸金債権の消滅時効が10年から5年と変更になりました。2020年4月1日より前の貸金債権の消滅時効は10年です。お金を貸した時期によって消滅時効の期間が変わりますのでご注意ください。)
- あなたが、催告したにもかかわらず、期限内に返済がなされないときは、例え利息に関する取決めがない場合でも、借主は、法律上年3%の割合による遅延損害金(利息)を支払う義務を負います。(注:民法改正により、2020年4月1日から法定遅延損害金が年5%から年3%に変更になりました。2020年4月1日より前の貸金債権の法定遅延損害金は年5%です。お金を貸した時期によって法定遅延損害金が変わりますのでご注意ください。)
- ここまでの手続で、借主から返済がなされなかったり、借主が返済についての話し合いに応じない又は、話し合いがまとまらないようなときは、裁判手続(訴訟、調停、支払督促など)を検討することになります。
- もし、借主が期限内に返済できなくても、あなたとの間で、返済日や返済方法などの条件について、話し合いがまとまったのならば、「合意書」ないし「和解書」を作成し、取交すのが良いでしょう。さらに、この時の約束を、簡易裁判所の手続き(訴え提起前の和解)や「公正証書」ですると、万が一、約束どおりの支払がなされなかった時、改めて訴えを起こして判決を得るなどすることなしに、借主の財産を差し押さえることができます。
Q. 家賃を滞納しているので、賃借人に出て行ってもらいたいのですが。
家賃滞納を理由に、賃貸借契約を解除して、明渡しを求めることができます。
- 但し、賃貸借契約は、お互いの信頼関係を基礎とするものです。たとえ契約書の中で「1回でも家賃を滞納した場合、何らの催告することなく直ちに契約を解除できる」などの取決めがあったとしても、その家賃滞納(契約違反)が、契約を継続し難いほどに信頼関係を破綻させているかどうかの判断によって、大家の側からの契約解除が認められないこともあります。少なくとも3~4か月以上の家賃滞納が必要になるかと思われます。
- したがって、まずは最初に、賃借人に対して、相当の期間を定めて、未払賃料の支払を催告します。その際に、もし期限までに支払がない場合は、賃貸借契約を解除することも併せて通知しておけば、支払期限が過ぎた後に、改めて契約解除の通知をする必要はありません。 これらの通知は、後日の裁判手続で、証拠資料となるので、配達証明付の内容証明郵便でするのが良いでしょう。
- もし、賃借人が期限までに未払いの家賃を支払わなければ、賃貸借契約は解除となりますが、賃借人が、自ら退去しないときは、裁判手続を検討することになります。
この時に、賃借人が退去しないからといって、無断で室内に立ち入ったり、勝手に家財家具などを処分したり、運び出してはいけません。そのような行為は不法行為にあたり、賃借人の損害を賠償しなければならなくなるおそれがあります。